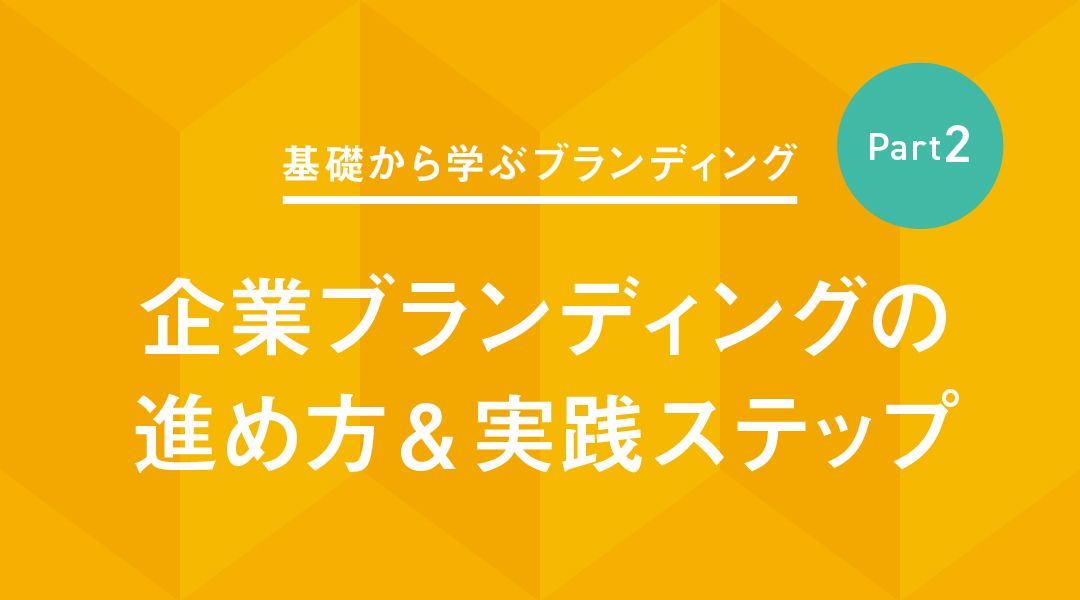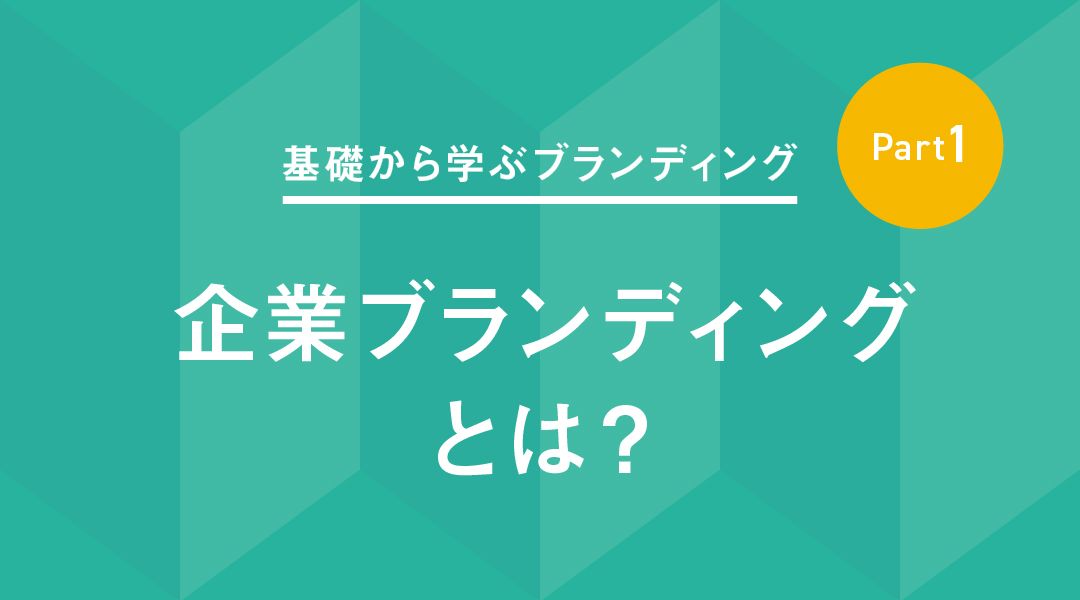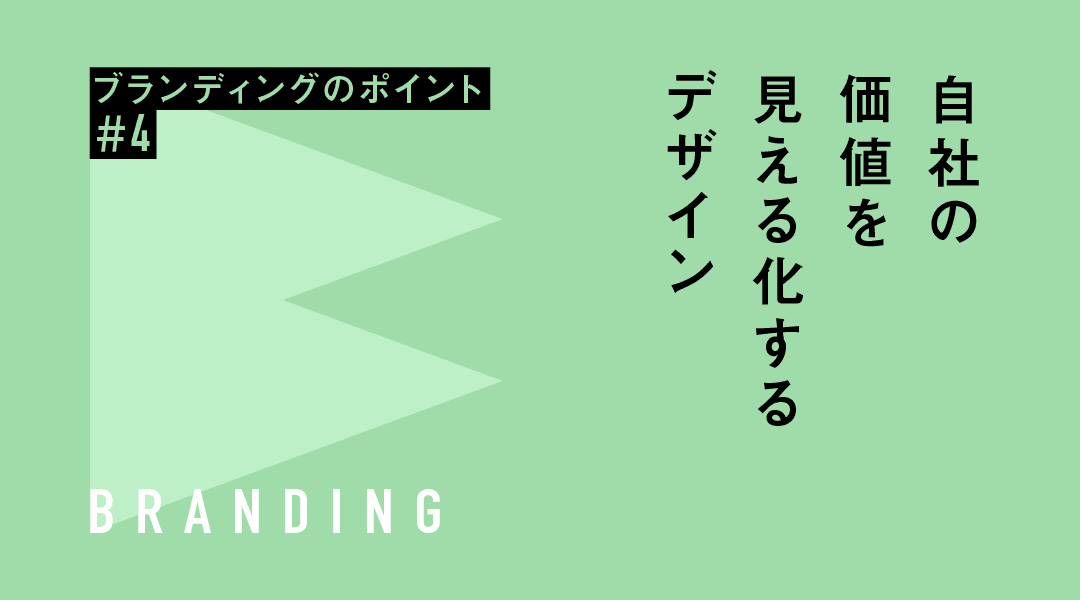チームの成長と停滞の分岐点【Part3.達成に導くスキルと仕組み】
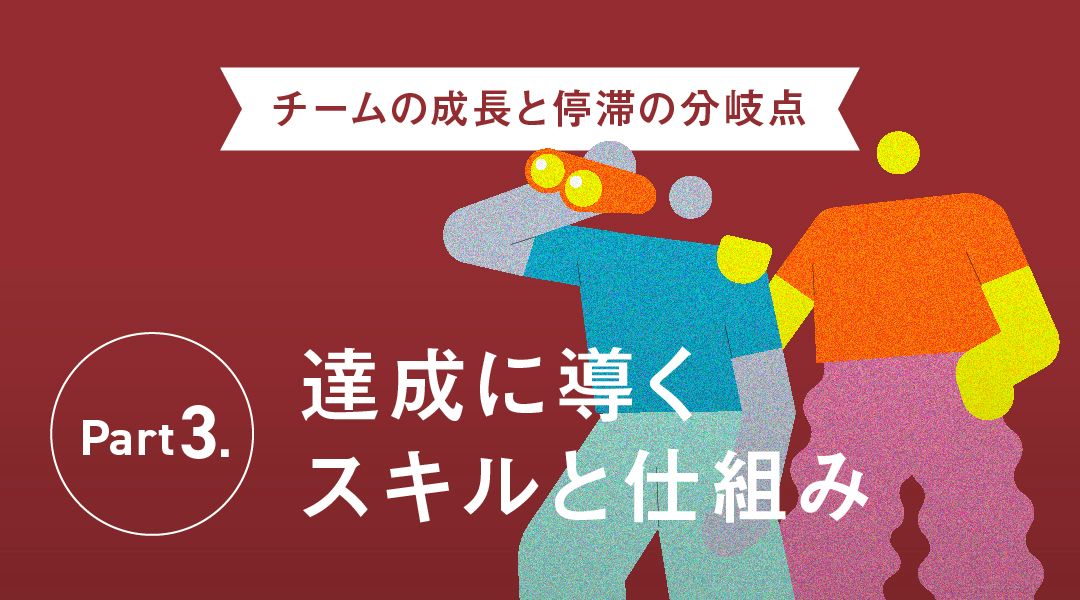
前回の記事では、部下とのコミュニケーション量を増やし、チームの心理的安全性を高めることの大切さについてお伝えしました。
コミュニケーション量を増やすといっても、何でもやみくもに話せば良いというものではありません。また、そのコミュニケーションを通じて部下が成長したり、目標達成に近づけるように導くのも上司の役割です。
目指すのは「仲良しチーム」ではなく、「成果を出すチーム」。
そこで上司の立場にある人は、以下の2つのポイントを意識していきましょう。
【2】部下が動くために必要な知識技術を教える「ティーチング」と、試行錯誤させる「コーチング」の使い分け
部下が「動ける」状態へ導く
「仕事なんだから、目標達成に向かって走るのが当然。」 「自分で考えてついて来てほしい」そう考えたくなる上司の方は、多いのではないでしょうか。これまで、ご自身がそうやって努力を積み重ねてきた経験があるからこそだと思います。
確かに、自走できる優秀な人材もいます。ただ、そうした人材が常にチームに加わるとは限りません。「自発的について来てくれる人」が前提になっていると、安定して成果を出すのが難しくなってしまいます。
たまたま良い人材が来たときには、結果が出る。けれど、そうでない時には「人材が足りない」「採用がうまくいっていない」といった外的要因に目が向いてしまう――そんな状況が続くと、今いるメンバーのモチベーションにも影響を与えかねません。
だからこそ、ゴールを明確にし、チームで共有することが重要です。会社や組織が目指す方向を理解し、それを言語化して部下に伝える。そして一緒に納得感をつくっていく。これは、上司だからこそ担える役割なのです。
◾️部下に達成イメージを持ってもらい、見失わないようにサポートする
◾️ゴールに向けた具体的な行動を明確にする
ここまで準備が整えば、部下も自信を持って動き出せるはずです。
「部下が動かない」という悩みは、実は「動けない」状態であることが多いもの。役割や担当範囲があいまいなままでは、動こうにも判断がつきません。動きやすい状態まで導くことが、上司としての支援のひとつです。
もちろん、「自分で考えて動けるようになってほしい」という想いはとても大切です。その実現のためにも、部下の状況や理解度に応じて、ティーチングとコーチングを上手に使い分けていくことが求められます。
ティーチングとコーチングの使い分け
部下に「自分で考えて動けるようになってほしい」と願うなら、まずは“考えるための材料”が必要です。つまり、最初は「教える(ティーチング)」が不可欠になります。
✔︎ 知識や基本的な技術がまだ十分でない場合 ✔︎ ルーチン業務に取り組むとき ✔︎ まずは型に沿って経験してもらいたい業務 ✔︎ 早期に成果を出す必要があるとき
業務の進め方や押さえるべきポイントを、上司が主体となって細かく伝えていくやり方です。
一方、「コーチング」は部下が主体。自主性を引き出すスタイルです。
✔︎ 試行錯誤の中で仕事の勘所を掴んでいってほしいとき ✔︎ 気づきや発想を大事にしながら、主体的に改善と学びを深めてほしいとき
この場合、上司は「指示する」のではなく、「聴く」「問いかける」ことで部下自身が課題に気づき、次の行動を考えられるようにサポートします。
部下の状況や成長段階に応じて、【ティーチング→経験→コーチング】をバランスよく繰り返していく。このプロセスが、やがて部下の自立につながっていきます。時間も手間もかかりますが、結局これが一番の近道なのです。
最近、1on1ミーティングに力を入れる企業が増えているのは、こうした指導を継続的に行うための手段として有効だからです。実際、それを丁寧に実践している企業ほど、組織としての成果も伸びています。
動きを引き出す「1on1」
1on1ミーティングに消極的な声の裏には、「忙しいから」だけでなく、「お茶を飲む雑談のような時間では?」というイメージが先行しているせいもあるのかもしれません。ですが、1on1は気持ちを共有する場であると同時に、仕事を前に進める場でもあります。
特に大事なのは、「次に何をするか」を明確にすること。「がんばれ!」「はい、がんばります!」のやりとりで終わるのではなく、目標に向かって「いつ・何を・どうやってやるか」を具体的に決めていきます。
目標達成のカギは、行動の細分化です。
やるべきことを小さく分け、頑張ったかどうかではなく、「できた/できなかった」がはっきり分かる単位にまで落とし込む。これが「行動分解」であり、1on1はそのための時間です。
育てる仕組みを整え、企業成長を加速
✔︎ 部下のやるべきことを明確にする✔︎ その達成に向けて、ティーチングやコーチング、行動分解で支援する
この2つが、上司の大きな役割になります。 そして、その仕組みとして有効なのが1on1ミーティングです。
「自分も現場で忙しい…」という状況は多くの組織で起きています。 でも、だからといって部下の育成を後回しにしてしまうと、チーム全体の成長も止まってしまいます。
時間とともに自然と信頼関係ができる……ように見えて、実は表面的な理解にとどまっているケースも少なくありません。成果を出せるチームになるためには、意図的なコミュニケーションと、明確な育成の仕組みが必要です。
また、中小企業にとって大切なのは、「勝てるビジネス」と「人を育てる仕組み」の両輪です。
人が育たない組織では、結局いつまでもプレイヤーとして経営者や上司が走り続けなければなりません。 個人に頼る体制には限界があります。
いわゆる「企業成長の壁(年商3億・5億・10億の壁)」を超えていくには、人を育て、役割を分け、組織を成長させるステップが欠かせません。
経営者や幹部が、人を育てることに目を向ける。 上司が、部下を育てることを「自分の仕事」だと認識する。
このマインドが組織全体に根づき、「育てる仕組み」まで整ったとき、中小企業はさらに力強く成長できるようになるのです。
チームの停滞に悩んだときには、ぜひこの記事のPart.1〜3を見直してみてください。
アドハウスパブリックでは、インナーブランディングをはじめ、新たな商品・サービスや事業開発などブランディングに関するさまざまなサポートを行っています。
競合他社とは一線を画し、圧倒的な支持を集め、一目置かれる存在。すなわち「ブランド」として広く認知されることを目指して、今こそブランディングに取り組みませんか?