『競争性』の特徴&活かし方【ストレングスファインダー®資質解説】|ALL BRANDING WORKS
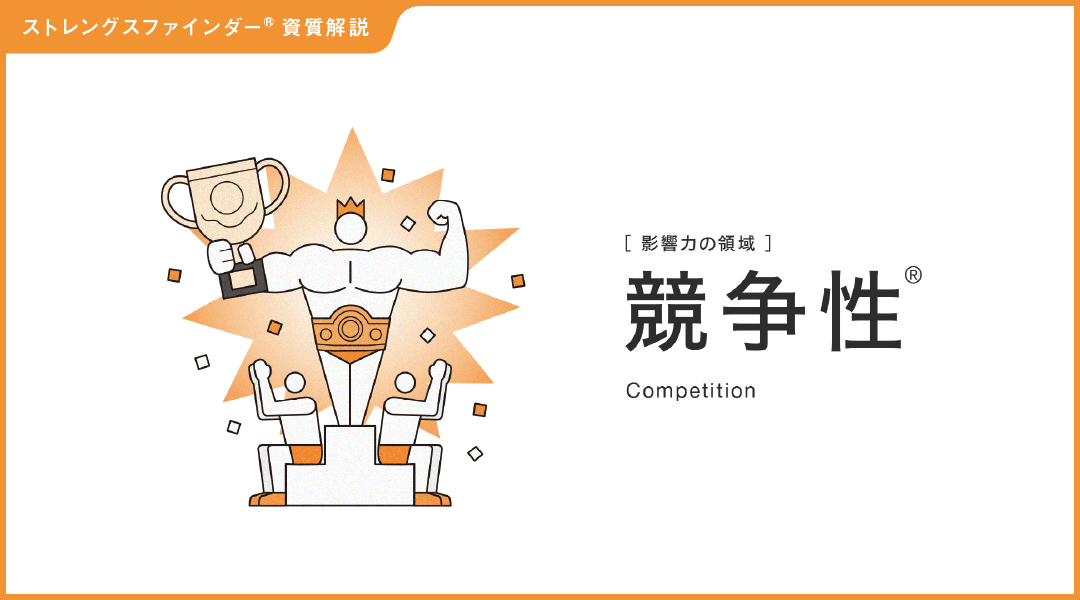
ストレングスファインダー®(クリフトンストレングス®)は、アメリカの世論調査会社Gallup社(ギャラップ社)が開発した「才能発見ツール」。Webテストで177個の質問に答えることで、自分の強みや才能を表わす「資質」を知ることができます。
この記事では、Gallup認定コーチが資質の特徴や活かし方を解説! 7,000人/200社以上のストレングスファインダー研修から得た経験と知識をお伝えします。
個人とチームのどちらにも活かせる内容ですので、ぜひ参考にしてみてください!
今回は34資質の中から、自分と他人を比較する『競争性』について解説します。
自分と他人を比較する『競争性』の特徴
『競争性』とは本能的に自分と他人を比較する人。 ライバルに勝つために努力を惜しみません。
競争性:Competition <影響力> TOP5出現率ランク:[日本]30位 [世界]27位
自然と比較や優劣を意識し、優秀であろうとします。 ゲームや勝負ごとが好きで、負けるのが人一倍嫌いな人でもあります。
- 自然に他人と比較をする。能力を見定める
- 負けたくない。勝つことに喜びを感じる
- 負けるのが予測できる勝負は挑みたくない
- 勝つため・優秀であるために努力する
- 優劣や順位など、数値で評価が表れることが好き
- 過去の自分の記録を越えようとする
- ライバルがいると刺激になる
- 二番手でも自分が許せない
『競争性』の源には、“比較”があります。自然に自分と他人を比べて“差”を見つけます。
ときには、比較対象が自分自身になることもあります。過去の記録や、できなかったことをできるようにすることで、自分との勝負に勝とうとします。
また、競争意識が強く、相手より「勝っていたい」という気持ちが原動力になります。負けている状態が嫌なので、人よりも自分が秀でているところを探したり、能力を磨く努力をします。

『競争性』のほかに併せ持つ資質によって、特徴が変わります。例えば、プランニングが得意な『戦略性』と組み合わさることで、作戦を立てることやそれにより勝利することにやりがいを感じる人もいます。また、第三者からの視線や評価がエネルギーにつながる『自我』を持つ人は、勝ったときの称賛をイメージすることで、モチベーションアップになることもあります。
以前、研修の受講生に『公平性』と『自我』を併せ持った方がいらっしゃいました。社会人でクロスカントリー競技のトップクラスの選手でもある方です。その方は、「順位も大切だが、正々堂々と戦うことをモットーにしている」「他人よりも過去の自分に負けたくないという気持ちがモチベーションだ」とおっしゃっていました。『競争性』と組み合わさった資質を感じる意見ですね。
このように、勝ち負けがモチベーションに関わる『競争性』は、“自分がエネルギーを発揮したくなるフィールド”を見つけることをオススメします。
人生の目的に合う仕事や、チャレンジしたくなる案件や資源が揃っている環境、努力を重ねても苦ではなくやりがいを感じられる分野に注力することで、有意義な時間を過ごすことができます。
『競争性』を上位にもつ人は、他者との関係性に“競争を持ち込みすぎない”ように注意しましょう。つい勝敗をつけたり、人に優劣をつけたがってしまう癖があります。
また、相手の向上心や競争意欲をもたせるために勝負ごとに仕立てたり、負けん気を刺激しようとする人がいますが、逆にやる気を低下させてしまうことがあるでしょう。誰もが競争を好むわけではありませんので、相手に合わせた対応が必要です。
『競争性』の長所と短所
ストレングスファインダーの資質1つ1つに2面性があります。才能が開発されて、長所や自他に良い影響を与える「バルコニー」の状態。もう1つが、未開発で短所として使われている「ベースメント」の状態です。
ここでは『競争性』のバルコニー/ベースメントの“あるあるネタ”をご紹介します。

●“勝ち”にこだわり勝率を上げる! 負けず嫌いな面があり、たとえ2位であっても許せません。“勝ち戦”が好きなので、始めから負けるのが目に見えている勝負は避けようとしたり、勝ち筋を見つけてから挑む傾向が強いです。エネルギーが湧く分野や、トップを目指したくなる環境を選び、競合分析や成功者のノウハウを学ぶなどして勝ち方を見つけましょう。自分の強み・弱みの把握もオススメです。「このやり方なら高確率で勝てる!」という勝ちパターンを作り、どんどん勝率を上げていきましょう。
●楽しみながら取り組むのが得意! 気が乗らない仕事や日々の生活にゲーム性を持たせることで、楽しんで取り組むことができます。例えば「事務作業を5分以内で終えられたら、ご褒美にケーキを食べる!」など、何かと競ったり、ライバルとの勝負にするなど “楽しむ工夫” をしましょう。
●勝つために努力を惜しまない! 負けず嫌いな性格から、業績などでトップ成績を目指したり、ライバル会社に勝つために努力します。目標を掲げるときは、やりがいを感じる“やや難易度が高い”目標にしましょう。低すぎては張り合いがなく、高すぎても達成できず、負け戦が続いてやる気が低下します。少し背伸びをするくらいの目標やライバルを設定し、攻略の過程や目標クリアを楽しむといいでしょう。

●望まない人を勝負に巻き込んでしまう 勝敗にこだわり過ぎる面があります。戦うからにはトップを目指し、2位以下は負けたも同然と見なします。しかし、勝負ごとに興味のない人や優劣をつけられるのに抵抗感を感じる人もいます。また「勝敗が全てではない」ということも、心に留めておきましょう。
●能力の低い人を見下してしまう 無意識に相手の能力を“評価する”傾向があります。優秀であることを良しとする考えを持っているため、能力が低い人や向上心がない人に対して低評価を下したり、嫌悪感を感じることもあるでしょう。しかし、あなたが見ているのは相手のほんの一部かもしれません。勝手な評価で相手の人格を否定したり、失礼な態度を取らないよう注意しましょう。
●勝ちにこだわりすぎてしまう 勝つために何をしても良いとは限りません。法を犯すことなどは言語道断ですが、あなた個人の判断だけでなくチームや組織の方針、メンバーへの配慮も忘れてはいけません。また、チームの士気や協調性を乱さないように気をつけましょう。
『競争性』の活かし方&モチベーション
資質を強みとして使い、生産的・安定的にパフォーマンスを発揮するようになるには、資質の深い理解と経験と知識を重ねながら、シチュエーションや条件、ベースメントの抑え方をマスターするなど、再現性を高めていくことが大切です。
『競争性』のモチベーションスイッチが入りやすいポイントを理解すると、スムーズに本来の力を発揮できるようになります。
ここでは一例をご紹介します。 ご自身で挑戦してみるもよし、『競争性』が高い人に対して試してみるもよし。ぜひ活用して、自分なりのスイッチの押しポイントをつかみましょう。
□ 作業を勝負ごとにして楽しむ要素をつくる □ トップを目指したい業界や分野・職種を選ぶ □ 競合分析や競合優位性をつくるなど、勝ち方を考える □ 評価基準を明確にする。業績や順位などを数値で見える化する □ 負け戦に参加しない(勝ち戦にできるように考える) □ 自身の能力開発のために何が必要か考える □ 刺激になるライバルを見つける □ ゲーム性を取り入れて、モチベーションを高める
これらは一例です。
『競争性』と併せ持つ上位資質によっても異なります。ぜひ、ご自身なりの得意技の繰り出し方を研究してみましょう。
『競争性』は、自分の勝ちパターンを見つけ、勝ち続けるサイクルを作ることで、高いモチベーションを維持できます。上記のような工夫を、できるだけ取り入れてみましょう。
勝つために何が必要かを考え、周囲にも協力を得ることで成果を出しやすくなるでしょう。サポートを求めたり、チームとのつながりを強めたいときは【人間関係構築力】カテゴリーの資質の人に相談すると良いでしょう。
『競争性』のマネジメント活用
「競争性」を上位にもつマネージャーが、リーダーシップや部下育成に資質を役立てていく際に、得意なスタイルがあります。①信頼関係構築 ②思いやりの示し方 ③安定感の生み出し方 ④希望の与え方と注意点 こちらの4つのポイントに沿ってお伝えしていきます。

①信頼関係構築:みんなで勝つ!勝利体験を促す チームに勝つ喜びを体験させることで一体感を作り出します。また、誠実な言動を心がけ、人への敬意や配慮を表すことで、真摯に挑む姿勢をメンバーに見せることができます。
②思いやりの示し方:競争を楽しめる雰囲気や仕組みをつくる 業績を求められることや、メンバー同士で優劣がつく場面にはプレッシャーがかかります。メンバーが楽しみながら目標や競争に挑めるよう、より良い仕組みや雰囲気をつくりましょう。努力を評価したり、結果を出したくなるようなインセンティブを設けるのも良いでしょう。
③安定感の生み出し方:意義や目的を伝える 業務が忙しくなるほど、目的を見失いがちです。意義や目標とのつながりを伝えることで、メンバーのモチベーションアップにつなげましょう。
④希望の与え方:メンバーの能力を活かす勝ち方を示す 『競争性』の人は、人の潜在的な能力を見抜く力があります。メンバーの長所や能力が発揮できる方法や配置・チームの強化ポイントをまとめ、“勝てる戦略”を示しましょう。

①競争を煽りすぎない マネージャー自身の「競争性」が高い場合は、競うことや他人と比較することを容易に受け入れられますが、誰もがそうではありません。人と比較されることや、競うことを強いられることで、モチベーションが低下する人もいます。自分自身と向き合うことや自分の成長を実感することで前進できることもあるので、「メンバー同士を競わせることが、成果を出す最良の方法だ」と決めつけないようにしましょう。
②メンバー同士が険悪にならないように注意する 優劣が出る・成績や順位がはっきりと表れる環境では、メンバー同士にストレスがかかりやすくなります。メンバー同士の関係性が悪くならないよう、気を配りましょう。また、結果が出ないメンバーの精神面を含めたサポートも考えましょう。批判するよりも、どうしたら成果が出るか、ともに考えましょう。
『競争性』のマネージャーは、メンバーが目標達成に意欲的になる方法を考えることができます。強みを活かして成果を出す方法や、成功体験を積ませることで、チームに自信をもたせることができます。
『競争性』資質のまとめ
『競争性』とは... 本能的に自分と他人を比較する人。ライバルに勝つために努力を惜しまない資質です。
こんな風に能力を発揮! ● 勝ちパターンを見つけて勝率を上げていく ● ゲーム性を取り入れてモチベーションアップ ● 勝つために目標に向けて努力する
資質を活かすためには、自分の勝ちパターンを見つけ、勝ち続けるサイクルを作ることが大切です。
ベースメントにはこう対処する! ● 望んでいない人を勝負に巻き込まない ● 能力の低い人を見下さない ● 勝ちにこだわりすぎない
下記のような状況で、『競争性』の資質を活かしやすく、活躍できるでしょう。
✓ 目指したい成績や目標がある仕事に就く
✓ 評価や達成基準が明確である環境を選ぶ
✓ 順位や成績がハッキリする環境を選ぶ
✓ 勝つためにチームの士気を高める起爆剤となる
✓ ライバルや競合の成績を超えたいとき
✓ 勝ち方を考える。戦略を立てる
✓ チームに勝つ喜びを伝える役割に就く
✓ 競合分析や競合優位性をつくるなど、勝ち方を考える
同じ資質を持っていても、他に持つ資質の組み合わせによって、一人ひとりの異なる使い方や、個性を生み出しています。
それぞれの資質について理解を深めながら、ご自身やチームのために強みを発揮できる機会を増やしていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
当社ではストレングスファインダーの活用セミナーやチーム研修を行っています。ご興味のある方は、こちらをご覧ください。


